この記事では、
嵐の名曲『PIKA★★NCHI DOUBLE』が「なぜこんなにエモいのか?」を、
コード進行・サビ構成・アレンジの観点から音楽的に紐解きます!
この記事では、
嵐の名曲『PIKA★★NCHI DOUBLE』が
「なぜこんなにエモいのか?」を、
コード進行・サビ構成・アレンジの観点から
音楽的に紐解きます!
「なぜ感情を揺さぶられるのか?」「その仕組みにどんな秘密があるのか?」
ファンとしての気持ちと、音楽的な分析を交えてお伝えしていきます。
この記事はアフィリエイトリンクを含みます。
この曲の“感動”はどこから来るのか?
私は中学生のころから嵐のファンクラブに入っている嵐ファンです。
王道J-POPの爽やかさを持ちながら、”感情を揺さぶられるような切なさ“を持ち合わせた
『PIKA★★NCHI DOUBLE』は嵐ファンの中でも“名曲”と言われています。
私自身も大好きな楽曲のひとつです。
この曲を聴くと、
“なんとも言えない”感動と切なさが胸に込み上げてくるんですよね。
この何とも言えなさを「エモい」と表現するなら、
『PIKA★★NCHI DOUBLE』はまさにエモすぎる一曲なのです…!
実際に、メンバーの大野智くんも過去の雑誌インタビュー(『月刊Songs』2004年3月号)でこう話していたそうです。
「コンサートのオーラスでこの曲を特別に歌ったんだけど、そのときめちゃくちゃ感動した。あれ不思議だったなあ」
「この曲、歌えば歌うほどいい曲なんだよね、何でだろう?」
引用元:青嵐 Blue Storm 大野智くん Fan Blog
嵐本人も「なぜか感動する」と感じる理由、
この曲の“エモさ”の正体は一体何なのでしょうか。
この記事で伝えたいこと
『PIKA★★NCHI DOUBLE』の“エモさ”は、決して気のせいではありません。
音楽構造(コード進行・構成・テンポ・アレンジ)に、
感情を揺さぶる“仕掛け”があります。
この曲に心が動く理由を、「感覚」ではなく「構造」で紐解く
それがこの記事の目的です。
『PIKA★★NCHI DOUBLE』の基本情報
- アーティスト:嵐
- リリース:2004年2月18日(嵐の12枚目のシングル)
- タイアップ:映画『ピカ☆☆ンチ LIFE IS HARDだけどHAPPY』主題歌
- キー(調):Dメジャー
- BPM:約150(やや疾走感のあるテンポ)
💡Dメジャーキー
Dメジャーは「明るさ」や「爽やかさ」を感じさせやすいキー。
しかし、この曲ではその明るさの中に、切なさや余韻が重なるように仕上げられている。
まずは聴いてみてください。あなたはどこで心が動きますか?
ぜひ一度、サビを中心に聴いてみてください。
リンクは👇に貼ってます。
「この曲の、心が動く部分はどこですか?」
公式配信リンク
*1分05秒くらいから再生すると、ちょうどよくサビです。
「騒ぎ出す」──このフレーズで心も騒ぐ
終わったはずの夢がまだ 僕らの背中に迫る引用元:『PIKA★★NCHI DOUBLE』作詞:SPIN・Rap詞:櫻井翔/作曲:森元康介/編曲:石塚知生
刻まれた想い出が騒ぎ出す
個人的にとても印象的なのは、サビの中の"騒ぎ出す"という歌詞の部分!
ちょうどこのタイミングで、ストリングスやギターが“シャーン”と4回鳴り響くんです。
こんな感じで👇(太字のところで鳴るイメージ)
さーわぎーだすーー
しかも、ここで鳴っているストリングスは
音階がどんどん上がっていくように聴こえます。
これも高鳴りを感じさせるポイントです!
MVでは、このリズムに合わせて手を突き上げるような振り付けがされています。
この振り付けも相まって、感情がより高ぶるような感覚になります。
そして、ラスサビは基本的に振り付けなしで、気持ちを込めて歌っているのですが
この”騒ぎ出す”のメロディーの部分だけは、同様の振り付けをしていますよね!
作り手側も、この部分を印象付けようとしているのが分かります。
コード進行とメロディの分析
ここからは、サビ前半のコード進行とメロディをセットで見ていきましょう!
曲の“エモさ”の源泉を、音楽理論の観点から紐解きます。
サビのコード進行
[G]終わったはずの夢
[A]がまだ
[D/F#]僕らの背中に
[Bm]迫 [D/A]る
[Em]刻まれたお
[F#sus4]もい [F#]でが
[Bm]騒 [A#aug]ぎ
[D/A]出す [G#m7-5]ー(伸ばし棒)
[G]終わったはずの夢
[A]がまだ
[D/F#]僕らの背中に
[Bm]迫 [D/A]る
[Em]刻まれたお
[F#sus4]もい [F#]でが
[Bm]騒 [A#aug]ぎ
[D/A]出す [G#m7-5]ー(伸ばし棒)
サビ前半のコード進行はこんな感じです。1行は1小節単位で書いています。
(コードはU-フレットと、以下の嵐公式の楽譜を参考に組み立てました。)
💡 コードとは?
複数の音を同時に鳴らして作る“響き”のこと。
基本は根音(ルート)・3度・5度の3音で構成され、特に3度が明るい(メジャー)・暗い(マイナー)を決める。
例:ド(根音)、ミ(3度の音)、ソ(5度の音) ←メジャーコードの場合
王道コードの中に潜む“影”
サビの始まりは、安定感のある「G」コードからスタートします。
このコード自体は明るく、穏やかな響きを持つ定番の和音です。
ところが、メロディには「C」や「C#」といった、コードに含まれない音が混ざっているんです。
🎼 コードにない音が意味するもの
・安定した「土台」の上に、ほんの少しだけ“不協和”が乗る
・結果として、「落ち着き」と「ざわめき」が同居する
→ このズレが、聴き手に“胸のざわつき”を生む
最初から「ただの明るい曲」では終わらない。
ここにすでに、エモさの種が蒔かれているのです。
“終わったはずの~迫る”の「G→A→D→Bm」の部分は、J-POPでよく使われるDメジャーの王道進行ですが、
この曲では、「D」を「D/F#」の分数コードにすることで一捻り加えているのがまたお洒落ですね!
💡 D/F# とは?
Dコードのベース音(一番低いコードの構成音)をF#にした形(分数コード)。
ベースラインが滑らかに下降し、メロディと調和しながら進行感を醸し出す。
不安定さを増す後半の進行
“刻まれた思い出が”の「Em→F#sus4→F#」は「Em」と「F#sus4」がポイント✨
このサブドミナントの代理コードからのsus4コードが緊張感や不安感を掻き立てて来るのです。
Dメジャーの世界では、サブドミナントに「G」(Gメジャー)を使うことが多いですが、 ここではあえて代理の 「Em」(Eマイナー) にして、まずは柔らかに切なさを引き込みます。
そして、後に続く「F#sus4」で一気に不安定さを出して感情を揺らしてくるのです…!
💡 サブドミナント・代理コードとは?
「サブドミナント」はキーのメインとなる音から4度上(または5度下)で、”動き”や”橋渡し”に使われるコード。
「代理コード」は共通音が多く置き換えが可能なコード。
代理コードは、自然な流れを作り出したり、本来のコードより柔らかい印象を与えたりする傾向がある。
💡 sus4コードとは?
「sus4(サスフォー)」はsuspended 4th(宙ぶらりんの4度)の略で、3度の音を4度の音に置き換えたコード。
コードの“雰囲気”を決める3度の音をあえて外し、4度の音を入れることで明るい/暗いが曖昧な、不安定な響きに。
この不安定さが「次にどう進むのか?」という期待感も生み出す。
さらに、「F#sus4」(F#–B–C#)というコードの上で、メロディーは「G(ソ)」を歌っています。
“思い出”の”も“の部分ですね。曲中で最も高い音です!
これはF#から半音上の音=♭9(フラットナインス)にあたります。
🎼心がざわつくポイント
・sus4コード自体が「明るい/暗い」が曖昧で不安定
・そこに♭9が重なることで、半音での強烈な緊張感が加わる
つまり「まだ解決しない不安定さ」と「鋭い衝突感」が同時に生まれます。
感情的には焦り・切なさ・胸がざわつく感覚として響き、サビの盛り上がりを一気にドラマチックにしているのです!
💡 ♭9(フラットナインス)とは?
コードのルート音(基準音)から数えて9度の音を、半音下げた音のこと。
例:「A」の♭9は「B♭」
この音が加わると、「強烈な不協和感」が生まれる。
そして次の「F#」は、「F#sus4」での切なさの頂点をギュッと解決する役割です。
「不安定 → 安定」の変化が感情を一気に高め、サビのクライマックスを彩ります!
曲全体の中で一番の高音=盛り上がりの部分で強烈な不安感を演出し、
それを解決させることで、この後の転換部分である”騒ぎ出す”をより効果的に魅せているように思います。
💡 解決とは?
音楽理論でいう解決(resolution)とは、不安定な響き(緊張)を安定した響きへ着地させること。
クライマックスの仕掛け
4和音が魅せる演出♪
“騒ぎ出す”
ここは前半の頂点であり、後半へ橋渡しする転換点。
「Bm → A#aug → D/A → G#m7-5」というポップスでは珍しい連鎖と、対応するメロディが、 高揚と未解決感を同時に作ります!
🎯 隠れたポイント:ベースの半音下降
「B → A# → A → G#」とベースが半音ずつ下がる“重力線”が全体を牽引。
コードが展開していく一方で、ベースラインが下降していく“二面性”は、サビ後半への予感や期待を膨らませます。
🎼イレギュラーなコード演出
・A#aug(増和音):不穏で未来が読めない感覚を演出
・G#m7-5(ハーフディミニッシュ):不完全な緊張感を残す響き
サビ後半で登場する A#aug(B♭aug) や G#m7-5(ハーフディミニッシュ)はノンダイアトニックコード です。
Dメジャーではないコードが入ることによって、意外性や感情の揺らぎを演出できます!
💡 augコードとは?
増三和音/オーギュメント(augmented)とも言われ、ルート・長3度・増5度で構成されたコード。
例:A#aug → A#–D–F♯
💡 m7-5/m7♭5(ハーフディミニッシュ)コードとは?
ルート・短3度・減5度・短7度で構成されたコード。次の展開への橋渡しによく使われる。
例:G#m7-5 → G#–B–D–F♯
augコードもm7-5コードも不安定でミステリアスな響きを持つのが特徴です!
💡 ノンダイアトニックコードとは?
ある調(キー)の中に含まれないコード。「切なさ」「不安定さ」を演出するのに多用される。
三位一体の強さ✨
コードの仕掛けに加え、冒頭でも述べたストリングスやギターのアクセントが入ることで、
感情の高まりをより感じられるドラマティックな印象を作り出しています。
- 不安定さのある、感情を揺らすコード
- コードに重なる等間隔のストリングスの音色→リズムとも同期
- リズムと盛り上がりを印象付ける振り付け
→結果:身体で「転換点だ」と分かる=エモの体感が最大化!
このサビが音楽的にも“エモい”理由
- 冒頭の安定感(G→A→D/F#)から徐々に緊張感を高める構成
- sus4やaug、m7-5など非日常感のあるコードを効果的に使用
- ストリングスの同期で感情を増幅
- 最後まで完全解決せず、余韻と次への期待感を残す
こうして見ると、聴き手の心を揺さぶったまま解放しない構造を持っているとわかります。
BPMは150と、比較的アップテンポな楽曲ですが、「楽しい」「明るい」「元気」「キラキラ」の印象よりも
「なんとも言えない切なさ」や「胸が締め付けられるような感覚」を感じる秘密はこのようなところにありそうです。
一見明るい曲なのに、ある意味裏切ってくる感じがまた、この曲の良さですね!
サビ構造の可視化
『PIKA★★NCHI DOUBLE』のサビは、ざっくりと4種類のフレーズが2度繰り返されるような構造になっています。
AとA’はメロディーが途中まで同じなのでまとめました。
1回目:A → A’ → B → C(展開)
2回目:A → A’ → B → D(終わり)
歌詞と照らし合わせるとこんな感じ👇
サビ前半(1回目)
A(出発)
[G]終わったはずの夢 → [A]がまだ
王道の進行(G→A)で明るく出発。ここまではキラキラな青春感。
A’(変化)
[D/F#]僕らの背中に → [Bm]迫 → [D/A]る
マイナーを挟むことで切なさが増幅。「迫る」という歌詞にピッタリな緊張感が生まれる。
B(転換)
[Em]刻まれたお → [F#sus4]もい → [F#]でが
サブドミナントの代理(Em)から半音進行(F#sus4→F#)で揺さぶる。
「思い出」という歌詞とリンクして、過去の記憶がせり上がってくるような感覚に。
C(未解決→展開)
[Bm]騒 → [A#aug]ぎ → [D/A]出す → [G#m7-5]ー ノンダイアトニックのA#aug、そしてG#m7-5で不完全に終わる。
「解決しない=終わりそうな青春をまだ終わらせたくない」という余韻を感じる、最大のエモポイント💡
サビ後半(2回目)
A(再出発)
[G]限られた愛と → [A]時間を
A’(変化)
[D/F#]両手に抱き → [Bm]しめ → [D/A]る
B(転換)
[Em]せめて今日 → [Asus4]だけ → [A]は 消え
サビ終わりに向かって切なさ+緊張を高めていく動き。
D(終わり)
[G]ない → [A]で
Dメジャーで「G → A → D」となれば着地感が強いのですが、あえて「A」で中途半端。
だからこそ続きがあるような、余韻を残す終わり方。
通常、キラキラ感の強いポップスは「終わり」の部分は解決させてスッキリ終わります。
しかしこの曲は「C:未解決 → D:終わりでも余韻を残す」という二重構造!
これが“終わらせたくない、けど限りある青春”を描いた「エモさ」を表現する音楽的トリックです!
PIKA★★NCHI DOUBEだけじゃない!類似のエモい曲
『PIKA★★NCHI DOUBLE』の「エモい構造」は、他にも共通する曲があります!(見つけました!)
BPMが150くらいで、“未解決感”や“切なさを強調するコード進行”を用いた、同じような印象を持つ楽曲をピックアップしました!
嵐の『PIKA★★NCHI DOUBLE』が好き!という方はこの2曲も刺さるかもしれません🙌
①King & Prince『Magic of Love』
2人体制になってから初のシングル『なにもの』のカップリング曲。
シングル曲ではないですが、ライブでも披露される曲です。
ノンダイアトニックコードが要所で使われ、切なさと高揚感を両立。
➡ 後日、比較記事を掲載予定です!
②コブクロ『君という名の翼』
サビで浮遊感のあるコード進行が使われ、疾走感と切なさを同時に演出。
まとめ:エモーショナル構造の発見
『PIKA★★NCHI DOUBLE』の“エモさ”は、歌詞の世界観だけではなく、
音楽構造そのものに仕掛けられた工夫から生まれていました。
- 王道感に影をもたらす分数コード(D/F#)
- 一番の高音に被せてくるsus4コード(F#sus4)で高まる緊張感
- ノンダイアトニックコード(A#aug・G#m7-5)による不安定さと感情の揺れ
- ベースラインの半音下降が作り出す「変化の予感」
- サビの4区分(A・A′・B・C/D)の構造と、終わりきらない余韻
- ストリングスやギターなどのリズムと同期した編曲
これらが組み合わさることで、「終わらないで欲しい青春」「有限感と切なさ」というテーマを音で体現しているのだと考察しました。
青春映画の主題歌という枠を超えて、多くの人が「なぜか感動してしまう」と感じる理由はここにあるのではないでしょうか!
最後に、この記事で触れた分析をヒントに、
みなさんも好きな曲を「コード進行」「サビ構造」「編曲の工夫」という観点から聴き直してみてください。
“この曲を聴くとこんな気持ちになるのはなぜ?”と考えてみると、
きっと新しい発見があり、さらに音楽が楽しくなるはずです🎵
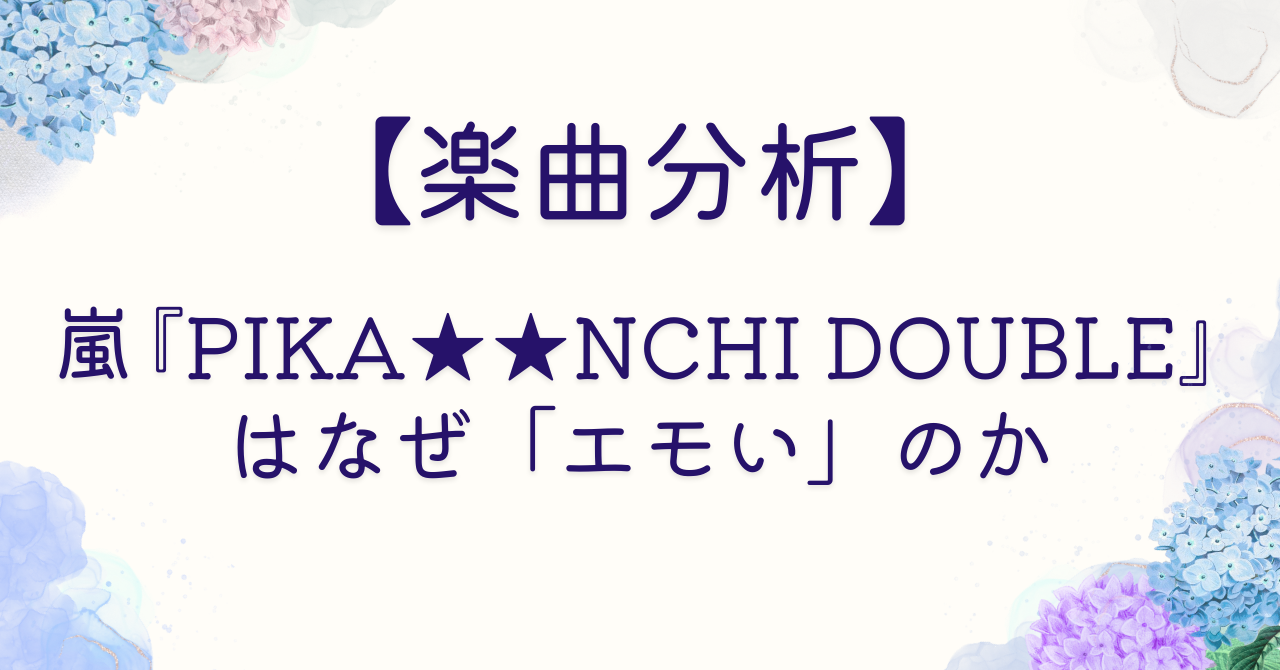


コメント